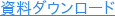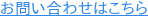本ブログでは、2024年に発表されたPhase 1への批判を振り返りながら、Phase 2が何を変えたのか、そしてOOH広告の評価軸が“アテンション”へと本格的にシフトする背景と意義を解説します。

■なぜ「Phase 2」が必要だったのか?
2024年に発表されたPhase 1では、OOH広告の測定指標が「OTS(Opportunity to See/視認機会)」に限定されており、実際に広告が“見られた”かどうかは評価されていませんでした。
これに対し、米国や英国のOOH業界からは以下のような懸念が寄せられていました。
- OTS依存の限界:単に「視界に入る可能性があった」という指標では、広告の効果や注視行動は把握できない
- 国際基準との乖離:WOO(World Out of Home Organization)が策定したグローバルガイドラインに反している
- 業界内合意の欠如:透明性に乏しく、メディア・広告主・代理店間の共通理解が得られにくい
今回のPhase2では、MRCはこうした批判も受けて「OOH広告のオーディエンス」を明確に定義し直し、ドラフトを公開、パブリックコメントを受け付けています。
■MRCが示す最終ゴール:OOHをクロスメディア評価の中へ
Phase 2の本質は、「OOH広告における接触を、テレビやデジタルと同様に取引可能な“オーディエンス”として定量化し、共通言語化する」ことにあります。
MRCが示す評価の階層構造は以下の通りです
■オーディエンスベースでの指標定義
Phase 2では、以下のようにAudience Impressionsを基準にメディア指標を再定義しています。
- Reach:一定期間内に広告に接触したユニーク人数(例:週次リーチ)
- Frequency:接触者1人あたりの平均接触回数
- GRP:Reach × Frequency(※Audienceベースの指標に限る)
LTSやOTSなどを基準に算出された値は補足情報(参考値)として扱うべきとされています。
■OOH広告測定における5つの重要な考慮点
MRCは、OOH広告に特有の測定上の留意点として、次の5点を挙げています。
- 1対多数の特性:OOHは「1人のユーザーに1広告」ではなく、「1広告が多数に同時に表示される」ため、個人ベースの測定モデルとは異なる設計が必要
- VACやEyes Onの活用と限界:既存のLTS指標(VACなど)は活用可能だが、Audienceとの混同はNG
- デジタル連携の注意:モバイルデータや位置情報などの補完的データは、オーディエンスや接触と同義ではない
- 技術革新の取り込み:AIなどの新技術により、LTSからAudienceへのブリッジが可能になる
- 多様なOOHフォーマット:空港・駅・観光地など、表示環境の多様性に応じたモデル構築が必要
なお、IAB/MRCが2025年5月に発表したAttention Measurement Guidelines(ドラフト版)では、広告接触を以下のように再構築しています:
- Attention Metrics(アテンション指標)は、表示時間だけでなく、視線の存在、滞留時間、スクロール速度などを組み合わせて評価
- OOHやTV、デジタルなどメディア横断で「実際に見られたか?」を定量化する方向に進化中
OOHもこの“アテンション計測”の流れに組み込まれる形で、MRCはPhase 2を設計しています。
■日本のOOH業界が今、取り組むべきこと
今回のPhase 2は米国の基準であり、まだドラフトではありますが、OOHの信頼性を国際水準で担保し、クロスメディアでの評価を可能にする変革と捉えると、日本のOOH業界にも以下の対応が求められると思います。
- VACに加え、アテンションを捉える新たな測定技術の導入(例:AI予測)
- 媒体社・広告主・代理店間での“指標リテラシー”の底上げ
- 他メディアとの比較可能性を意識した共通指標への移行
「表示された広告」ではなく、「実際に見られた広告」こそが、これからのOOH広告の価値を証明するスタンダードになるのです。